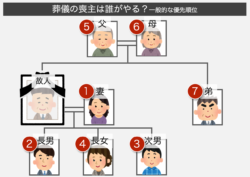本来葬儀はお別れの時間を共有することで故人を悼み、ご家族の悲しみの心を癒すものなので、他に重要な予定があったとしても葬儀への参列を優先するのが筋でしょう。
しかし誰もが新型コロナウィルス 感染する可能性が依然として否めない今、三密を避けるため葬儀への参列を自粛が余儀なくされ、心苦しく思っている方も少なくないと思います。
そのためこの状況下で葬儀に参列できない方への配慮として、オンライン葬儀が急速に広まってきました。
コロナ禍における勤め人のワークスタイルとして、リモートワークがメインとなりつつあります。それと同様に葬儀でも、ソーシャルディスタンスを順守しやすいオンラインでという考えが、一般的になりうる可能性はあるのではないでしょうか。
今回は葬儀の新しい形である、オンライン葬儀について確認してみたいと思います。
オンライン葬儀とは

オンライン葬儀は、海外在住などで簡単に移動できない方や、介護施設に入居している方など葬儀に参列するのが難しい場合に、PCやスマートフォンなどの携帯端末から、SkypeやZoom、LINEなどのビデオ通話アプリを使って、葬儀の様子をライブ映像で配信し、リモートで葬儀に参列してもらうサービスのことです。
オンライン葬儀の歴史
オンライン葬儀は、リモート葬儀、ネット葬儀、Web葬儀などと呼ばれることもあり、実に10年ほど前から日本でも始まっていました。その例として次のようなサービスが誕生しました。
- ドライブスルー葬儀場(車上焼香システム:上田南愛昇殿)
- どこでもお墓参(金剛宝寺樹木葬「天空陵」)
残念ながらオンラインでの葬儀が日本人のメンタルに合うわけもなく、一般的な葬儀の選択肢に加えられることは今までありませんでした。
オンライン葬儀に突然市民権が
新型コロナウィルスが、今までの常識を一気に塗り替えました。葬儀形態も例外ではありません。
今まで忌み嫌われ、キワモノとまでいわれたオンライン葬儀を私たちは受け入れざるを得なくなったのです。2020年4月の緊急事態宣言発令後、多くの葬儀会社ではオンライン葬儀対応を始めました。三密を避けるにはオンライン葬儀がベストであり、コロナ禍では唯一安全な葬儀方法とまで言われるようになりました。
オンライン葬儀のメリット
オンライン葬儀を行うことで、どのようなメリットがあるでしょうか。代表となるメリットを3つあげてみましょう。
1. インターネット環境があれば、オンライン葬儀に参列できる
オンライン葬儀は葬儀会場からのライブ配信なので、インターネット環境があれば、どこからでも葬式に参列することが可能です。
オンライン葬儀に合わせて香典、供花、供物などの手配や支払いまで、全てオンラインで完了できるオンライン葬儀専用システムの用意があることがほとんど。
もちろん喪主もオンライン葬儀システムを使って、返礼品も手配できるためほぼ全てのことが完結できるのです。
2. 実際の葬儀の進行と同じタイミングで、オンライン経由で弔問できる
もちろん家族や親族、そして僧侶は実際の葬儀会場にいますが、それ以外の参列者は読経、焼香、出棺など葬儀全ての式次第を、オンライン経由でリアルタイムに参加できます。
葬儀場や寺院の対応では、カメラとインターネット環境さえあれば、誰でも葬式の動画を撮影して配信できるので、必ずしも専門のスタッフがいなくても対応がすることが可能です。
またオンラインのライブ配信に加えて、葬儀から納骨までを1日で終わらせ、費用面の喪主の負担を削減させる取り組みも行なっている葬儀会場や寺院もあります。
3. オンライン葬儀にはリラックスして参列できる
葬儀では故人をしのぶことに没頭したいところですが、会場ではどんな方に会うかわかりません。そのため余計な気疲れをすることもありますが、オンライン葬儀なら他の人を気にすることなく、故人を送り出すことができます。
オンライン葬儀のデメリット
残念ながら、オンライン葬儀には、次のようなデメリットもあります。
1. 条件を満たしたインターネット環境がなければ始まらない
地方や高齢者の家庭では、インターネット環境がないケースも。それではオンライン葬儀に参加することは不可能です。またネットワーク回線の速度が遅いと、ライブ配信が途中で止まってしまうこともあるので、ある程度の回線スピードが必要になります。
2. オンライン葬儀への偏見
「葬儀をオンラインで行うなんて言語道断」というのが、日本人が元来持つ価値観といえるので、特に高齢者の方に拒否されることが十分に考えられます。
あるいはライブ配信では誰でも見られてしまうと心配し、セキュリティ面で懸念する方もあるでしょう。オンライン葬儀を行う場合には、セキュリティの確保と、事前に関係者の理解を得る必要があります。
3. オンライン葬儀の目的を誤る
「手間をなくしたい」「費用を安くしたい」などの理由で、オンライン葬儀を行うのでは故人は浮かばれません。オンライン葬儀を行う目的を明確にし、より丁寧な気持ちで臨むべきでしょう。
オンライン葬儀の方法
実際にどのようにオンライン葬儀を行うのか、その方法を確認してみましょう。
1. オンライン葬儀のプロセス
オンライン葬儀も、通常の葬儀と同じように進めます。ライブ配信で使用するシステムは、葬儀会社によりますが、ほとんどの場合SkypeやZoom、LINEなどが多いようです。参列者が使い慣れているアプリが別にあれば、葬儀会社への相談をお勧めします。
通夜まで
- 人が亡くなると、死亡診断書が医師により発行
- 死亡診断書の用紙の左側が死亡届なので、必要事項を記入
- 死亡から7日以内に、各市町村役場に死亡届を提出。受理されると火葬許可書が発行
- 葬儀会社に連絡し、オンライン葬儀を希望する旨伝える(コロナ禍で対応ができる葬儀会社が増えているが、確認は必要)
- 電話や郵便、あるいはメールで葬儀の案内を行う。その中にオンライン葬儀の参列に必要なアプリのダウンロードや、設定のインストラクションも含める
通夜
- オンライン葬儀の場合も、開式、僧侶による読経、弔辞弔電、お焼香、閉式という流れで進行
- 香典はオンラインで送り、ライブ配信で式次第を見ながら参列。細かい進行は葬儀会社の指示に従う
- 通夜振る舞いをオンラインでする場合には、会場、各自の自宅で準備
告別式
- 開式、僧侶による読経、弔辞弔電、焼香、式中初七日、閉式、出棺、火葬、収骨をライブ配信経由で見守る
- 通夜振る舞いと同様、精進落としについてもオンラインでつないで行う場合があり
告別式以後
納骨や四十九日法要、一周忌法要など、その後の供養はオンライン葬儀でも通常の葬儀と同様に行う
2. オンライン葬儀の費用相場
一般的な葬儀費用の主な内訳は葬儀一式の費用、飲食費用、寺院の費用(戒名料含む)で、地域にもよりますが、70万円~150万円が相場と言われています。家族葬なら50万円~100万円といったところです。
一方オンライン葬儀の場合は、通常の葬儀にオンライン葬儀サービス利用料をプラスすることになりますが、サービス料は0円~50,000円。家族葬+オンライン葬儀の場合、50万円~100万円で行うことができるようです。
オンライン葬儀のマナーと注意点

最後にオンライン葬儀のマナーと注意点について確認しましょう。
1. 服装:見えないからといって気を抜かない
オンライン葬儀の場合、参列者は画面に映りませんが、それだからといって普段着でよいということではありません。故人と遺族に失礼がないように、喪服またはそれに準じた服装で参加するべきでしょう。
2. 香典:原則的には送る
オンライン葬儀であっても原則的に香典は送りますが、喪主から香典辞退があった場合にはそれに従いましょう。
3. 弔電、供花、供物:オンライン葬儀サービスを利用
一般的な葬儀同様の対応です。弔電では言葉を選ぶのも同じです。いずれの場合も、オンライン葬儀サービスで対応している場合には、通常より簡単に対応できるでしょう。
4. オンラインでの会食:通常の会食と同様の姿勢で
オンライン飲みのようにカジュアルすぎるのはNGです。オンライン葬儀の会食では、その場にふさわしい会話、服装で参加するべき。無論通常の葬儀の場合と同じですね。
ニューノーマルでのオンライン葬儀
今まで受け入れられ難かったオンライン葬儀。コロナ禍が終止したとしても、今後はニューノーマルにおける葬儀の選択肢の一つになると考えられます。
オンライン葬儀だからといって軽んじることなく、マナーはきちんと守った上で参列しましょう。どんな葬儀形態であれ、大切なのはいかに故人を思って送り出せるかということなのです。遺族の方の悲しみを和らげる意識を持って、他の参列者への感謝の気持ちも忘れずに。