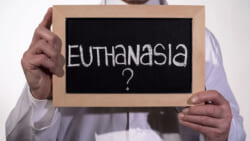相続は多くの人にとって人生で一度あるかないかの経験であり、複雑な法律や税金の問題が絡むため、専門家のアドバイスが必要不可欠です。
そして、相続に関する相談は複数の専門家で可能です。専門家ごとに得意不得意があり、サービスの対応範囲や費用も異なります。
まずは、いきなり専門家に相談を依頼する前に、無料相談を活用することをおすすめします。
相続に関する無料相談について詳しく解説し、各専門家の特徴や選び方、注意点などをまとめてご紹介します。
もくじ
相続の無料相談とは?

相続の無料相談とは、相続に関するさまざまな問題や疑問について、専門家に無料で相談できるサービスのことを指します。
無料相談サービスは、市区町村の自治体や法律事務所、税理士事務所などが提供しており、相続手続きの流れや遺産分割の方法、相続税の計算など、幅広い内容について相談することができます。
相続の無料相談を活用するメリットをご紹介します。
・費用をかけずに専門家のアドバイスを受けられる
・相続に関する基本的な知識や情報を得られる
・自分の相続案件の複雑さや専門家への依頼の必要性を判断できる
・有料サービスを利用する前の予備知識を得られる
無料相談は通常、30分から1時間程度の時間枠で行われ、基本的な質問や相談に対応します。ただし、具体的な書類作成や詳細な相続計画の立案などは、有料サービスとなる場合が多いので注意が必要です。
| 無料相談の基本的な対応範囲 |
| ・相続手続きの全体的な流れ ・相続人の確定方法 ・遺産分割の方法や注意点 ・相続税の概算計算 ・遺言書の作成や効力 ・相続放棄や限定承認の手続き ・相続に関する紛争解決の方法 ・不動産の相続登記手続き |
相談内容は、相談者の状況や相談先の専門家によって異なる場合がありますが、基本的な情報や方向性を得ることができます。
相続の無料相談窓口の種類と特徴

相続に関する無料相談を行う専門家には、さまざまな種類があります。それぞれの専門家によって得意分野や対応範囲が異なるため、自分の相談内容に最適な専門家を選ぶことが大切です。
相続の無料相談ができる主な専門家の種類と特徴、選び方について解説します。
市区町村の無料法律相談
多くの市区町村では、住民向けに無料の法律相談サービスを提供しています。市区町村の相談は、主に弁護士や司法書士などの法律の専門家が担当し、相続に関する基本的な質問や相談に対応します。
| 特徴 | ・地域住民であれば誰でも利用可能 ・予約制が多く、相談時間は通常30分程度 ・基本的な法律相談に対応 ・相続以外の法律相談も可能 |
| 利用方法 | ・市区町村の公式ウェブサイトや広報誌で相談日程を確認 ・電話やウェブサイトで予約 ・指定された日時に相談場所(市役所や公民館など)に来訪 |
市区町村の無料法律相談は、相続に関する基本的な情報を得るのに適していますが、専門的な相談や具体的な手続きについては、ほかの専門家に相談することをおすすめします。
また、相談内容によっては、より専門的な相談窓口を紹介してもらえる場合もあるので、積極的に質問することをおすすめします。
弁護士による無料相談
多くの弁護士事務所では、初回無料相談を実施しています。弁護士は法律の専門家であり、相続に関する法的な問題や紛争解決に強みを持っています。
| 特徴 | ・法律全般に精通し、相続に関する法的アドバイスが可能 ・遺産分割協議や相続争いの調停 ・訴訟に強い ・複雑な相続案件や紛争がある場合に適している |
| 対応範囲 | ・遺産分割協議の進め方 ・相続人間のトラブル解決 ・相続放棄や限定承認の手続き ・遺言書の作成 ・検認 ・相続に関する訴訟や調停の手続き ・相続財産の調査や評価 ・相続税の基本的な説明 |
| 得意分野 | ・相続争いの解決 ・複雑な遺産分割 ・相続に関する法的手続き ・相続人の権利保護 |
| 向いているケース | ・相続人間で争いがある場合 ・複雑な遺産分割が必要な場合 ・相続に関する訴訟や調停が必要な場合 ・法的な観点からの相続対策を検討したい場合 ・相続放棄や限定承認を検討している場合 |
弁護士による無料相談を選ぶ際は、相続専門の弁護士を探すことをおすすめします。また、初回無料相談の内容や時間制限についても事前に確認しておくとよいでしょう。
弁護士に相談するメリットは、やはり幅広い法的なアドバイスを受けることができる点です。とくに、相続人同士で揉めていることがある場合は、力強いサポーターになってくれます。
一方で、税金関係や登記手続きなどに関してはほかの専門家の方が詳しいことが多いです。そのため、弁護士による無料相談を利用する際は、相談内容を事前に整理し、法的な観点からどのようなアドバイスが必要かを明確にしておくとよいでしょう。
税理士による無料相談
税理士は税務の専門家であり、相続税の計算や申告、節税対策などに詳しい専門家です。多くの税理士事務所でも弁護士事務所同様に、初回無料相談を実施しています。
| 特徴 | ・相続税の計算や申告に関する専門知識がある ・財産評価や節税対策に強い ・相続税が発生する可能性がある場合に適している |
| 対応範囲 | ・相続税の概算計算 ・相続財産の評価方法 ・相続税の申告手続き ・相続税の節税対策 ・生前贈与の活用方法 ・相続時精算課税制度の説明 ・事業承継に関する税務アドバイス |
| 得意分野 | ・相続税の計算と申告 ・財産評価 ・相続税の節税策立案 ・相続に関する税務調査対応 |
| 向いているケース | ・相続税の発生が予想される場合 ・相続財産の評価が難しい場合(事業用資産や不動産など) ・相続税の節税対策を検討したい場合 ・相続税申告の必要性を確認したい場合 ・生前贈与を活用した相続対策を検討したい場合 |
税理士による無料相談を選ぶ際は、相続税の専門知識を持つ税理士を探してください。近場で専門知識を持つ税理士が見つからない場合は、ホームページのお問い合わせフォームなどから、「相続税に関する相談は可能か?」と質問するとよいでしょう。
税理士に相談するメリットは、相続税に関するアドバイスを的確に受けられることです。金額によっては、莫大な追徴課税が発生することもあるため、確実に正しく納税するならば税理士のアドバイスは受けるべきでしょう。
ただし、税務以外の相続手続きは対応していないため、相続に関して幅広い相談をしたい場合は向いていません。
また、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)に注意し、早めに相談することをおすすめします。
司法書士による無料相談
司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所への提出書類作成などを専門とする法律の専門家です。相続に関しては、主に不動産の相続登記や遺産分割協議書の作成などを得意としています。
| 特徴 | ・不動産の相続登記手続きに強い ・遺言書の作成や保管に関するアドバイスが可能 ・相続に関する各種書類の作成に詳しい |
| 対応範囲 | ・不動産の相続登記手続き ・遺産分割協議書の作成 ・遺言書の作成 ・保管 ・相続放棄や限定承認の手続き ・相続人調査 ・相続財産管理人選任申立て ・相続に関する裁判所への各種申立て手続き |
| 得意分野 | ・不動産の相続登記 ・遺産分割協議書の作成 ・相続に関する各種書類作成 ・相続手続きの全体的なサポート |
| 向いているケース | ・不動産の相続登記が必要な場合 ・遺産分割協議書の作成が必要な場合 ・遺言書の作成や保管について相談したい場合 ・相続手続き全般について相談したい場合 ・相続に関する裁判所への申立てが必要な場合 |
司法書士による無料相談を選ぶ際は、相続登記や遺言書作成の経験が豊富な司法書士を探すことをおすすめします。
また、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)に伴い、今後はますます相続登記に関する相談が増えることが予想されるため、早めに相談することが賢明です。
なお、相続税や複雑な法律問題については、ほかの専門家の方が詳しい場合があるため、不動産関係の相続がある場合に相談するとよいでしょう。また、相続登記以外の相続手続きについても質問がある場合は、司法書士事務所のホームページなどで事前に相談可能な範囲を確認しておくとよいでしょう。
行政書士による無料相談
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や相談業務を行う専門家です。相続に関しては、遺言書の作成や相続手続き全般のサポートを得意としています。
| 特徴 | ・遺言書の作成に強い ・相続手続き全般のサポートが可能 ・各種行政手続きに詳しい |
| 対応範囲 | ・遺言書の作成 ・相続手続きの全般的なアドバイス ・相続に関する各種書類の作成 ・相続財産管理人の選任申立て ・相続に関する行政手続きの支援 ・生前対策(任意後見契約、財産管理委任契約など) ・死後事務委任契約の作成 |
| 得意分野 | ・遺言書の作成 ・相続手続きの総合的なサポート ・相続に関する行政手続き |
| 向いているケース | ・遺言書の作成を検討している場合 ・相続手続き全般について相談したい場合 ・相続に関する行政手続きについて相談したい場合 ・生前対策や死後事務について相談したい場合 ・相続に関する書類作成のサポートが必要な場合 |
遺産を相続する際は、非常に多くの行政手続きを行なわなければなりません。行政手続きは複雑で専門知識を必要とする難解な内容も多いです。もしも間違いがある場合、さまざまな窓口でたらい回しにされることも珍しくありません。
行政書士は相続に関する複雑な行政手続きを、専門知識を活かして徹底的にサポートしてくれます。自身で用意しなければならない書類もありますが、行政書士で手続きを代行してもらうことも可能です。
また、法的に効力のある遺言書の作成も可能であるため、生前から相続に関する相談をすることができます。
行政書士による無料相談を選ぶ際は、相続や遺言に関する経験が豊富な行政書士を探すことをおすすめします。
ただし、法律や税務の複雑な問題については、ほかの専門家の方が詳しい場合があるため、対応範囲に注意して相談をしましょう。もしもその他に相談したい内容がある場合、行政書士からほかの専門家を紹介してもらえることもあるため、聞いてみるのもよいでしょう。
相続の無料相談を利用する際の注意点

無料相談は基本的に時間に限りがあり、規定以上の時間や回数を過ぎると有料になります。より効率的に無料相談を活用するためには、予めある程度の準備をすることが大切です。
相続の無料相談を利用する際の注意するべきポイントを解説します。
相談内容を整理しておく
無料相談の時間は限られているため、事前に相談内容を整理しておきましょう。
整理するべき内容をリストアップいたしましたので、ぜひ参考にして相談内容を決めてください。
・相続人の状況(誰が相続人か、相続人間の関係など)
・被相続人との続柄
・相続人の人数と年齢
・相続人間の関係性(良好か、対立があるかなど)
・相続財産の内容(不動産、預貯金、有価証券など)
・不動産の種類、所在地、おおよその評価額
・預貯金の金融機関名と概算額
・有価証券の種類と概算額
・その他の財産(生命保険、美術品、貴金属など)
・被相続人の遺言の有無
・遺言書の有無
・遺言書がある場合、その形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
・遺言書の内容(わかる範囲で)
・相続に関する具体的な悩みや疑問点
・遺産分割の方法について
・相続税の発生可能性と対策
・相続手続きの進め方
・相続人間のトラブルについて
・相談で解決したい事項
・最も優先度の高い問題
・具体的に知りたい情報や手続き
・専門家に依頼するべきかどうかの判断材料
なお、相談内容を整理したリストは、有料相談に移行する際も大いに活用できます。性格に情報を共有し、漏れなく相談できるようになるので、無料相談をする前にリストを作成しておきましょう。
相談先を比較する
相続の無料相談を提供している専門家や事務所は多数あります。より適切な対応を受けるために相談先を比較することをおすすめします。
比較の際に見るべきポイントをご紹介します。
・自分の相談内容に合った専門分野を持つ専門家か
・相続案件の取扱い実績や経験年数
・口コミやレビューを参考に、対応の丁寧さや分かりやすさを確認
・相談場所へのアクセスの良さや、オンライン相談の有無
・無料相談の時間制限(延長可能な場合の料金)
・複数回の無料相談の可否
・対面、電話、オンラインなど、希望する相談方法に対応しているか
・無料相談後の有料サービスの料金体系
・対応可能な業務範囲
複数の相談先を比較することで、自分のニーズに合った最適な専門家を見つけることができます。また、実際に相談してみて、相性や信頼感を確認することも大切です。
まずは候補をいくつか絞ってから、無料相談を利用してみましょう。
無料相談後の対応も確認する
無料相談は、あくまでも初期段階の相談です。相続手続きを進めていくうえで、有料のサービスが必要になる場合があります。
もしも無料相談終了後に有料で依頼する場合、どのような対応が行われるかを必ず確認しましょう。
無料相談後の対応で確認するべきポイントをご紹介します。
・有料サービスの具体的な内容
・有料サービスの料金体系(着手金、報酬金、時間制など)
・着手金の有無と金額
・報酬金の計算方法(定額制、財産額に応じた報酬など)
・時間制報酬の場合の時間単価
・追加で発生する可能性のある費用(実費など)
・今後の相続手続きの流れと、必要な作業の概要
・相続手続きの全体的なスケジュール
・各段階で必要な作業と書類
・相続人が自分で行える作業と、専門家に依頼すべき作業
・次回の相談や依頼の方法
・次回相談の予約方法
・連絡手段(電話、メール、専用のポータルサイトなど)
・対応可能な時間帯や休業日
・契約内容や重要事項の説明
・契約書の内容確認
・解約条件や中途解約時の取り扱い
・守秘義務や個人情報の取り扱いについて
・他の専門家との連携体制
・必要に応じて他の専門家(税理士、弁護士など)と連携できるか
・連携先の専門家の紹介が可能か
・アフターフォローの内容
・相続手続き完了後のサポート体制
・相続税申告後の税務調査対応
・相続関連の書類の保管サービスの有無
無料相談後の対応も確認しておくことで、より自身の相談内容に合った専門家を選べるようになるでしょう。
よくある相続相談の内容

相続の無料相談では、さまざまな内容の相談が寄せられます。中には同じような内容を相談される人も多いです。
相続の無料相談にてどのような内容を相談しているのか、よくある内容をまとめてご紹介します。
遺産分割についての相談
遺産分割は、相続人間で相続財産をどのように分けるかを決める重要なプロセスです。遺産分割に関する相談では、以下のような内容が多く見られます。
| カテゴリ | 相談内容 |
| 遺産分割の進め方 | ・遺産分割協議の開始時期 ・協議の進め方や注意点 ・遺産分割協議書の作成方法 ・相続人間での話し合いの方法 ・円滑な話し合いのコツ ・意見の対立がある場合の対処法 ・第三者(専門家)の介入の必要性 |
| 遺産分割協議書の作成方法 | ・必要な記載事項 ・作成時の注意点 |
| 有効な遺産分割協議書の条件 | ・相続人の1人が遺産分割に応じない場合の対処法 ・説得の方法 ・調停や審判の申立て ・相続人の不在や所在不明の場合の対応 ・特別受益や寄与分の考慮方法 ・特別受益の範囲と算定方法 ・寄与分の認定基準と主張方法 |
| 調停の申立て方法と流れ | ・審判に移行する場合の条件 ・調停や審判にかかる費用と期間 |
専門家に何か作業をしてもらうのではなく、「どうしたらいいですか?」とアドバイスをもらう目的で相談されています。
遺産分割に関する相談では、弁護士や司法書士の無料相談を活用するとよいでしょう。
相続税についての相談
相続税に関する相談は、とくに財産規模が大きい場合や不動産を相続する場合に多く見られます。無料相談でよくある相続税についての相談内容をご紹介します。
| カテゴリ | 相談内容 |
| 相続税の計算方法 | ・基礎控除額の計算 ・相続税の税率 ・相続税の総額と各相続人の納付税額の計算 |
| 相続税の申告期限と手続き | ・申告に必要な書類 ・申告書の作成方法 |
| 相続財産の評価方法 | ・土地の評価方法(路線価方式、倍率方式) ・建物の評価方法 ・株式や事業用資産の評価方法 |
| 相続税の節税対策 | ・生前贈与の活用 ・相続時精算課税制度の利用 ・小規模宅地等の特例の適用 |
| 相続時精算課税制度の活用方法 | ・制度の概要と適用条件 ・相続税の納税方法 ・一括納付と延納の選択 |
| 物納の条件と手続き | ・納税資金の準備方法 ・相続税の配偶者控除 ・配偶者控除の適用条件 ・控除限度額の計算 |
| 実務上の注意点 | ・事業承継における相続税の特例 ・事業承継税制の概要 ・適用条件と手続き ・特例適用後の継続要件 |
相続税は金額が大きくなる場合もあるため、適切な節税対策を行うことで負担を軽減できる可能性があります。そのため、無料相談は積極的に活用するべき内容だと言えるでしょう。
相続税に関する相談は、税金の専門家である税理士に依頼しましょう。
遺言書の作成についての相談
遺言書は、相続において被相続人の意思を明確に伝えるための重要な書類です。
ドラマやアニメなどの作品では、内容と署名のみが書かれたカジュアルな遺言書が登場しがちですが、法的効力を持つ遺言書を作成するには決まった形式で書く必要があります。
そのため、自分の死後に相続を希望通り進めて欲しい人が、遺言書の作成について相談するケースが多いです。
無料相談でよくある遺言書の作成についての相談内容をご紹介します。
| カテゴリ | 相談内容 |
| 遺言書の種類と特徴 | ・遺言書作成時の注意点 ・遺言書の作成方法 |
| 遺言執行者を選任する際のポイント | ・遺留分への配慮 ・遺留分を侵害しないようにするための注意点 ・遺留分侵害額請求が発生した場合の対応 |
| 特定財産の指定 | ・不動産や預貯金など、特定財産を指定する際の注意点 ・相続人間で公平性を保つための方法 |
| 遺言書保管制度の活用 | ・法務局による遺言書保管制度の概要 ・保管制度を利用するメリットと手続き方法 |
| 相続時精算課税制度の活用方法 | ・制度の概要と適用条件 ・相続税の納税方法 ・一括納付と延納の選択 |
| 生前贈与との併用 | ・生前贈与と遺言書を併用する場合の注意点 ・節税効果や相続人間でのトラブル回避策 |
| 遺言書作成後の変更や撤回 | 遺言内容を変更したい場合の手続き撤回する際に注意すべき点 |
遺言書作成に関する相談は、行政書士や司法書士が得意としています。公正証書遺言の場合は、公証人との連携が必要になるため、専門家に依頼するとスムーズです。
また、弁護士に相談すれば、法的な観点からより詳細なアドバイスを受けることができるでしょう。
不動産相続についての相談
不動産は相続財産として非常に重要であり、評価や手続きは複雑になることがあります。そのため、無料では対応しきれない範囲も多いですが、無料相談を活用してスムーズに手続きを進めることも可能です。
無料相談でよくある不動産相続についての相談内容をご紹介します。
| カテゴリ | 相談内容 |
| 不動産の評価方法 | ・路線価方式や倍率方式による評価 ・固定資産税評価額との違い ・不動産鑑定士による評価が必要な場合 |
| 相続登記手続き | ・相続登記義務化(2024年施行)の概要 ・相続登記に必要な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など) |
| 登記申請時の注意点 | ・共有名義となった場合の対応 ・共有名義によるデメリット(売却時や管理時の問題) ・共有名義を解消する方法(持分売却や分割) |
| 不動産売却による現金化 | ・売却時に必要な手続きと費用 ・売却益に対する課税(譲渡所得税)の計算方法 ・売却後の資金分配方法 |
| 小規模宅地等の特例適用 | ・特例適用条件(居住用宅地、事業用宅地など) ・特例による減額効果と申請手続き |
| 賃貸物件や収益物件の場合 | ・賃貸物件を相続した場合の管理方法 ・賃貸契約継承時の注意点 ・収益物件による相続税対策 |
| 不動産管理や維持費について | ・相続後に発生する固定資産税や維持費 ・管理会社への委託が必要な場合 |
| 土地活用による節税対策 | ・土地活用(アパート建設など)による節税効果・活用計画立案時に注意すべき点 |
不動産相続については、司法書士や税理士が専門的な知識を持っています。不動産登記手続きをスムーズに進めたい場合は司法書士、不動産評価や節税対策について詳しく知りたい場合は税理士に相談するとよいでしょう。
無料相談の予約方法

相続相談を無料で受けるためには、予約が必要になることが多いです。無料相談の主な予約方法について解説します。
電話で予約する
電話予約は最も一般的な予約方法です。電話予約時の一般的な流れをご紹介します。
1.相談先(市区町村窓口、弁護士事務所など)の電話番号を確認する。
2.営業時間内に電話をかける。
3.担当者に希望日時を伝える。
4.相談内容を簡単に説明し、適切な担当者がいるか確認する。
5.予約完了後、日時と場所をメモする。
電話予約では直接質問できるため、不明点があればその場で確認できます。ただし、営業時間外では対応してもらえないことがあるので注意しましょう。
オンラインで予約する
オンライン予約は近年増えている便利な方法です。オンライン予約時の一般的な流れをご紹介します。
1.相談先(弁護士事務所、市区町村窓口など)の公式ウェブサイトへアクセスする。
2.無料相談予約フォームを見つける。
3.必要事項(氏名、連絡先、希望日時など)を入力する。
4.相談内容や希望事項も記入して送信する。
5.確認メールまたは電話連絡を待つ。
オンライン予約はインターネットを利用するため、34時間365日、いつでもどこでも申し込みできるメリットがあります。
自分の都合に合わせて予約できるうえに、多くの場合では自動返信メールで予約内容が確認できるため、間違いも少なく便利です。
直接窓口に行く
直接窓口へ訪問して予約する方法もあります。直接窓口に行く場合は、その場で担当者と話しながら詳細な情報を得られるメリットがあります。
直接窓口に行く場合の一般的な流れをご紹介します。
1.窓口所在地と営業時間を確認する。
2.必要事項(身分証明書など)があれば持参する。
3.窓口担当者に無料相談希望である旨を伝える。
4.希望日時や相談内容について話し合う。
5.予約完了後、その場で確認事項を書面でもらうことも可能。
とくに自治体の窓口では、直接訪れる人は少なくないですが、事前予約を徹底しているケースもあるため注意が必要です。また、基本的には予約を優先されるため、窓口で長時間待たなければならないことも多いです。
相続相談を受けるタイミング

有料無料問わず、相続相談はベストなタイミングで行うことで、より効率的でスムーズに相続を進められるようになります。
相続相談を受けるタイミングについて解説します。
遺産分割が始まる前
遺産分割協議が始まる前に相談すると、スムーズな話し合いにつながります。具体的には以下の場合がおすすめです。
・相続人間で意見調整が必要になる場合
・相続財産が複雑である場合(不動産、有価証券など)
・被相続人が残した財産状況について詳しく知りたい場合
できるだけ早めに専門家へ相談しておくことで、トラブル回避につながります。
トラブルが発生したとき
相続トラブルが発生した際は、速やかに専門家へ相談しましょう。
・相続人間で意見対立が起きた場合
・特定財産について法的紛争になりそうな場合
・過去の生前贈与や借金など複雑な問題が絡む場合
トラブルが長引くことで、期限内に相続税を納められなかったなどの問題に発展することもあります。そのため、トラブルになりそうなときは、弁護士など法的紛争解決能力を持つ専門家へ速やかに依頼することをおすすめします。
手続きがわからないとき
相続手続きは、専門家に依頼しなくても進めることはできます。しかし、複雑な部分が多いため、どのように進めたらいいのかわからなくなった場合は、専門家へ相談して的確なアドバイスをいただきましょう。
・必要な書類や提出先について不明点がある場合
・財産評価や登記手続きを自分で進める自信がない場合
・税務申告期限内に間に合うか不安な場合
相続手続きに関しては、司法書士や行政書士から具体的なアドバイスを受けられます。とくに行政手続きに関しては、行政書士の得意分野なのでぜひ活用しましょう。
無料相談から有料相談への移行時の注意点

無料相談から有料サービスへ移行する際には、それぞれの違いについて認識しておくことが大切です。
無料相談から有料相談への移行時に確認するべき注意点をまとめてご紹介します。
| 無料サービス範囲 | 無料サービスでどこまで対応可能か |
| 有料サービス内容 | 具体的な業務範囲・料金体系・契約条件など |
| 契約前説明 | ・契約書の内容(業務範囲、料金体系、支払い方法など) ・解約条件や中途解約時の取り扱い ・業務完了までのスケジュールと進捗管理方法 ・守秘義務や個人情報の取り扱いについて |
| 料金体系の透明性 | ・着手金や報酬金の金額と支払いタイミング ・時間制報酬の場合の時間単価と見積もり総額 ・実費(交通費、書類作成費用など)の有無と金額 |
事前に確認しておくことで、有料サービスへの移行時にトラブルを防ぎ、安心して手続きを進めることができるでしょう。
まとめ

相続に関して専門家に相談する場合、それぞれ料金は異なるものの、相応の費用が必ず発生します。そのため、専門家に相談した方がよいのか、どの専門家に相談するべきかなどを判断する際に、無料相談は大いに役立ちます。
状況によっては、無料相談でいただいたアドバイスだけで、相続手続きを終わらせることも可能です。
まずはどの専門家に相談するべきか相談内容を整理して、自分に合った方法で申し込むところから始めてみましょう。
また、無料相談の有無や条件は相談先によって異なります。詳しい内容は各相談先へ確認しましょう。