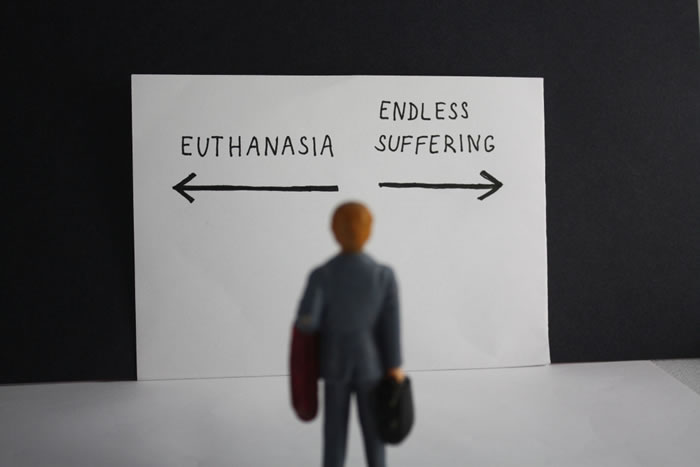
尊厳死という言葉は、世界的に共通する定義を持ちません。死という全ての人間に共通することなのにも関わらず、対応が国によって異なるのはその問題が複雑であるということです。
尊厳死をめぐる議論について、日本と世界の現状を分かりやすく解説します。
さまざまな取り組みに触れることで、尊厳死・安楽死を考える際に役立つ内容です。さらに尊厳死・安楽死という言葉にひそむ危険についても言及しています。
■尊厳死を考える~もくじ
- 尊厳死1.尊厳死とは何か|尊厳死の歴史や安楽死・自然死との違いを解説
- 尊厳死2.尊厳死・安楽死をめぐる議論|日本と世界の現状を解説
- 尊厳死3.尊厳死を迎えたいと思ったら・・・|あなたの尊厳が守られるためにすべきこと
- 尊厳死4.大切な人が尊厳死を望んだら|家族にできること
- 尊厳死5.大切な人を看取る|最期のときがきたら
もくじ
安楽死という概念の歴史
英語で安楽死は「euthanasia」と表され、ギリシャ語の「良き死」が語源とされています。
このギリシャ語は単に「死」の状態を表しており、良き死のために誰かが何かをするという意味はなく、良い死はどのようなものかという意味も含みません。
耐え難い苦痛から救われるために死を選択するという考え方を最初に公にしたのは、イギリスの思想家トマス・モアと言われています。
1516年、彼は著書『ユートピア』の中に以下の言葉を記しました。
『病が永遠不治で絶え間のない猛烈な苦しみを伴うものであれば、司祭と役人は相談の上で病人に向かって思い切って、その苦しい病気と縁を切ったらどうかと死を勧める。そして、十分に納得した病人は、絶食するか眠っている間に死んでゆき、それは名誉あるものと信じられる。これに反して、司祭や市会が承認する前に自ら命を断ったものは土と火を持って葬るに相応せぬものとしてその死骸は泥沼の中に捨てられる。』
現在多くの場合に用いられている、耐えがたい苦痛に苦しむ患者を死なせるという意味として安楽死という言葉が広く用いられるのは1860年代からです。
第2次世界大戦中のナチスドイツでは、成立はしなかったものの「治癒不可能な病人における死の封助に関する法」という法案が存在しました。
この考えのもと障害者などを「安楽死(euthanasia)」として秘密裏に大量虐殺した歴史があります。この法案はヒトラーが指導したのではなく、当時の医師らが提案したものです。
このイメージが強いため、英語圏では「euthanasia」という単語があまり使われなくなり、「Doctor-assisted suicide(医師による自殺ほう助)」、「mercy killing(慈悲の殺人)」、「death with dignity(尊厳のある死)」などが用いらるようになりました。
諸外国の安楽死法と呼ばれているものは日本語に意訳されているだけで、実際には「安楽死」という言葉は用いられていません。
尊厳死の歴史
安楽死と似たような言葉に尊厳死があります。この歴史に関しては別の記事で詳しく紹介しています。
世界の尊厳死・安楽死
2019年のデータに基づいて解説します。治療の差し控えは日本を含めて多くの国で認められており、医師によって患者を死なせる、自殺ほう助が許されている国は世界的にも数えるほどです。
▼医師によって患者を死なせる、患者の自殺ほう助の両方が可能な国
オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダ
▼医師によって患者を死なせることが可能な国
コロンビア
▼医師によって患者の自殺ほう助が可能な国・地域
スイス、アメリカ(オレゴン州、ワシントン州、モンタナ州、バーモント州、カリフォルニア州、コロラド州、ワシントンDC、ハワイ州、ニュージャージー州、メイン州)、オーストラリア(ヴィクトリア州)
オランダの法律
『要請による生命終結及び自殺幇助の審査手続並びに刑法典及び埋葬・火葬法の改正に関する法律』
2001年に成立し、世界で初めて医師によって患者を死なせることや自殺ほう助が許される法律です。これらを実施する要件は以下の通り。
- 患者の希望が自発的なものであり、熟考の末であることを確認する
- 患者の苦痛が耐えがたいものであり、改善の見込みがないことを確認する
- 患者に状況を説明し、今後の予想を伝える
- 患者とよく話し合い、双方がほかに適切な解決方法がないと納得する
- 患者にかかわりのない他の医師少なくとも1名の意見をきく。相談を受けた医師は患者と面接し、上記1~4について注意義務基準が満たされているとみなす旨を書面にする
- 患者の生命を終結させる、あるいはその自殺介助を行うについて、適切かつ慎重な医療を実施する
この法律では患者の意図しない殺人などの事件を防ぐために、亡くなった後の報告や審査も規定しています。
家族でも口出しできないほど自己決定を重んじる国民性もありますが、医療制度も大きな要因です。保険診療のほとんどを家庭医が担っているのです。
国民は家庭医に登録し、何かあったら家庭医に相談するのが基本。そこから必要であれば専門医などが紹介される仕組みなので、家庭医は患者のすべての病歴を把握していることになります。
安楽死を行うのもこの家庭医で、患者と家庭医の密接な関係も世界初の法律の制定に影響していると言えるでしょう。
スイスの法律
スイスには医師による死への介助に関する法律はありません。刑法の解釈によってそれが許されています。
刑法第115条 自殺への誘導・ほう助
利己的な理由によって誰かを自殺するようあおる、あるいは、自殺するのをほう助する者は、その自殺が実際に行われた、あるいは試みられた場合、5年以下の懲役刑か罰金刑が科される。
この条文は「利己的な理由によって」とされることが特徴です。遺産を得る、恨みを晴らすなどの理由でなければ自殺ほう助は解釈上、罪に問われません。
1982年に自殺ほう助をする民間団体が設立されました。現在は複数の団体が活動をしています。
刑法の解釈ではスイス国民に限っているわけではないとして、外国人も自殺ほう助をすることができます。最高裁判所がその要件を明らかにしていて、適切に行われたかどうか調査するシステムもあるのです。
自殺ほう助の団体はカウンセリングや社会的支援も行っており、それによって意思を変える人も少なくありません。
カルフォルニア州の法律
『自然死法』1976年に成立しました。「Natural(自然な) Death(死) Act(法律)」という名称なので、日本語ではこのように訳されています。
これは終末期においての延命治療の指示を、判断能力のあるうちに患者が書面で表す権利があるというものです。患者の意思を表現する方法としてリビング・ウィルを法的に認めました。
この法律では医師による薬液の投与や自殺ほう助は認めていません。日本では法的根拠はないものの、患者の意思を表すものとして医療現場などではリビング・ウィルが用いられています。
2016年には『終末選択肢法』が施行され、回復の見込みのない患者が医師に致死薬を処方してもらう権利が認められ、医師による自殺ほう助が可能になりました。
尊厳死や安楽死の議論を始める前に

尊厳死や安楽死には明確な定義が存在しません。つまり「尊厳死に賛成か反対か?」という問いがあった場合、それがどのような行為を示すのかは曖昧なのです。
例えば「オランダの医師が行う患者の死への政策の賛否」であれば明確になります。議論をする相手が示す尊厳死や安楽死と自分の思うそれとが同じであるかどうか確認する必要があります。
書籍や論文を読む場合も同じことが言えます。どのような条件におけるどのような行為なのかを明らかにすることが重要です。
日本における尊厳死・安楽死議論の争点
現在の日本における議論の争点を解説します。
日本では医師による殺人や自殺ほう助はいかなる場合においても認められていません。終末期医療に関しての法律もなく、そもそも患者の権利に関する法律もありません。
しかし耐え難い苦痛に苦しむ患者は実際に存在します。医師が殺人や自殺ほう助で起訴されるケースもありました。
そこで厚生労働省は人生の最終段階における医療やケアの決定は患者の意思を最大限に尊重するという医療従事者向けのガイドラインを2007年に公表し、2018年に改訂。
法整備には時間がかかるため、やむを得ない措置ともいえます。医療やケアの決定は本人の価値観を共有することが大切であり、家族や医療従事者と繰り返し話すことが重要とされています。この過程はアドバンス・ケア・プランニングといい、厚生労働省では人生会議と名前をつけました。
このガイドラインの概要は、下記の通りです。
- 可能な限りの苦痛の緩和を行う。身体だけでなく、精神や社会的な援助も行う
- 患者や家族に十分な情報を提供する
- 患者や家族と医療・ケアチームが繰り返し話し合う
- 患者の意思の変更を想定した話し合いとする
- 医療・ケアの開始や不開始、変更、中止などはチームで妥当性を検討する
- 患者の意識がない場合においては代理人が決定することができる
しかし、このガイドラインは多くの課題も指摘されています。スイスの刑法の解釈のように、細かく決められていないからこそできることもあるからです。
制限が少ないほど患者は自由に選択することができるため、十分な体制が整えられるなら細かいガイドラインは必要ないかもしれません。しかし現在の医療体制では限界もあり、それが課題の要因となっています。
このガイドラインの課題として以下の点が挙げられます。
- 人生の最終段階の定義や医療・ケアの定義がないため判断が難しい
- 患者や家族が話し合いに耐えられるかという懸念がある
- 医療従事者でない患者や家族が現状を把握し、今後を想像するだけの知識が得られるか定かではない
- 現行の医療体制で、医療従事者が話し合いに十分な時間をとることができるのかという問題
- あらゆるケースを想定することは困難で、選択した結果が予想外の状態になるおそれがある
- 医師の免責が明らかでないため、医師は殺人や自殺ほう助で起訴されるのではと懸念している
このガイドラインだけでは、現場の医療従事者が実際に行動することは難しいでしょう。そのため病院ごとに仕組みを作ることになり、医療にばらつきが生じてしまう懸念もあります。
緩和ケアとの関係
緩和ケアとは病気の治癒を目指すのではなく、今ある症状を緩和しようという医療行為を指します。痛みや呼吸困難、吐き気などの身体的なものだけでなく、不安や抑うつといった精神的なものも含む医療行為です。
さらに、社会的な問題や宗教的な問題、家族の問題などもケアの対象になります。患者自身の苦痛の原因となるあらゆるものを緩和しようというものです。
その一つにセデーション(鎮静)があります。末期のがんで予後が2週間以下と予想され、これまでのケアでは耐え難い苦痛を緩和しきれない場合、患者を眠らせるというもの。
間欠的に眠らせるという方法もありますが、場合によっては、亡くなるまで眠ったままということもあるのです。このように眠らせるケースと、医師が患者をすぐに死なせるというものと何が違うのかという議論もあります。
さらにセデーションはがん患者以外には行われません。それ以外の病気で苦しむ人と不平等が生じているのではないかという意見もあります。
尊厳死・安楽死の裏側〜言葉がもたらす誤解
「尊厳死」「安楽死」という言葉。実は非常に危険な要素があります。
「延命治療の差し控えや中止」「医師による自殺ほう助」「医師による嘱託殺人」といった行為自体は「尊厳死」「安楽死」という言葉ができる前から存在していました。
耐え難い苦痛から逃れるために自ら死を選ぶ自死(自殺)もずっと昔からあります。
絶望的な苦しみへの最終手段として死があったということは容易に想像できることでしょう。自殺は現在も法律を犯す行為ではありません。
では、自殺ほう助や殺人はどうでしょうか。これは、多くの場合罪に問われます。そして、やむを得ない事情があった場合は、酌量の余地があると判断されます。
そのやむを得ない事情のひとつが回復の見込みがなく、耐えがたい苦痛のある人に対しての行為です。
つまり、自殺ほう助や殺人の一部だけ切り取られて名前が付けられたのが「尊厳死」「安楽死」ということになります。
これは報道などにおける利便性もありますが、尊厳死や安楽死を広めようとする人々の策略だという意見もあるのが実情です。ナチスドイツの用いた「euthanasia」を避け、複数の言葉が生まれていることからも考えられます。
WHO憲章では健康の定義を示していますが、安楽死や尊厳死の定義はしていません。
実態があいまいなものに名前がついてしまったというのは大変危険です。議論する際に論点がずれるだけでなく「何となく分かった気になってしまう」ため。
「尊厳死」と聞いて悪いイメージを持つ人は少ないでしょう。「よさそうなことなのだから、反対する必要もないよね」と考えて思考停止してしまうことが最大の懸念点なのです。
諸外国の法律では多くの場合「医師による命の終結」「自殺ほう助」「死への補助」などといった表現が用いられています。
法律は行為の内容自体を取りしまるものなので、より具体的な単語をしようする必要があるので、日本語で表現する場合に意訳として尊厳死や安楽死と表現されているだけにすぎないのです。
自己決定の落とし穴
各国で行われている医師による死の補助は患者個人の自己決定が最も重要だとしています。あなたがとても辛くて死にたいのなら、医学的に妥当だと判断されればお手伝いしますよということです。
「自分で決めたこと」は本当に良い選択だったといえるでしょうか。
選択するということは他の選択肢を捨てるということです。「もしあのとき違う選択をしていたら・・・」と考えたことはありませんか?
自分が強い意志で死を望んだとして、それが本当に自分自身による決定だという確証はありません。
人は社会の中で生きており、人との関わりに中で存在しているため、他者から影響を受けてます。その決定をする上で十分な知識のもとしっかりと考えたのかという問題もでてくるでしょう。
治療の中止が予想以上の苦痛を伴った、生きていれば感じられた喜びがあったかもしれないなど、不確定要素が多いです。
結婚は離婚ができます、就職は転職ができます。しかし死ぬのは死に直すことができません。「この間、安楽死したんだけどね、こんな感じだったよ」と言える人はひとりもいないのです。誰も分からないことを自己決定するということは予想以上に難しいことであると言えます。
尊厳死や安楽死は医療の問題だけではない
もし病気に苦しむ人の苦痛が全て取り払われたら、その人は死を望むでしょうか。たとえ身体に苦痛があっても心が満たされていたら死を望むでしょうか。
最終手段の死を選ぶ前に、本当にすべての手を尽くしたのかと考えることも重要です。
「家族に迷惑がかかるから」
「お金がないから」
「たとえ生きていても楽しいことはないから」
「もう誰の何も役にたたないから」
などということは医療だけでは解決できません。
「死にたい」と思う時、それは単純に身体的な苦痛が原因だけではないでしょう。
闘病が家族にとって多大な負担ではなかったら、経済的な心配が全くなかったら、毎日小さな楽しみを感じられていたら、死にたいと思うのでしょうか。
確かにすべての問題を解決することはできません。しかし、医療以外の政策で対応ができるものもあるはずです。尊厳死や安楽死を考えるときにはこういった広い視野を持つことも重要になります。
法整備がされてない日本だからこそ活発な議論が未来を切り開く
日本の終末期医療は諸外国に比べて遅れていると批判する人がいます。法体制が整っていないという意味ではそうかもしれません。
しかし外国の法律がさまざまであるように、この問題には絶対的な答えはありません。それにも関わらず、医療という規則の中で行われるため、細かいルールの徹底が求められているのも事実です。
尊厳死や安楽死という言葉にとらわれずに、死は苦痛からの解放になるのか、殺人や自殺ほう助が許され場合があるのか、自分はどのような死を望むのかなど活発に議論することが大切なのです。
日本ならではの見解があってよいのです。「縁起でもない」と死を話すことを避ける風習もあります。しかし、この議論を避けて後悔するのは自分なのかもしれないのです。




















