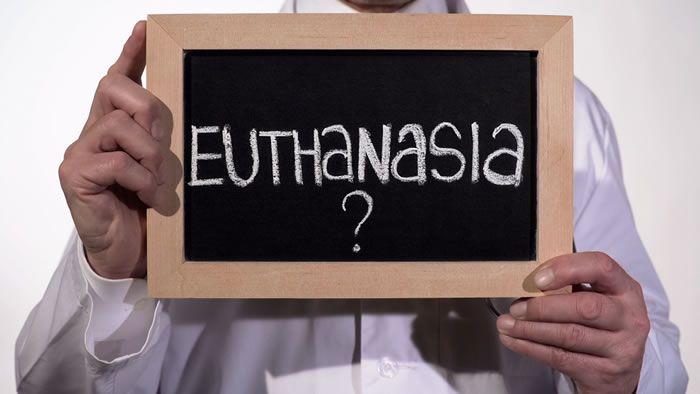
尊厳死を希望するあなたは「最期は穏やかでありたい」「効果のない延命治療はしてほしくない」と考えているのではないでしょうか。
もしくは、「あのような死はいやだ」と避けたい死のイメージがあるのかもしれません。
人生の最期を自分らしくありたいと望むのは当たり前のことです。尊厳死を迎えるに何をすればよいのかを解説します。
■尊厳死を考える~もくじ
- 尊厳死1.尊厳死とは何か|尊厳死の歴史や安楽死・自然死との違いを解説
- 尊厳死2.尊厳死・安楽死をめぐる議論|日本と世界の現状を解説
- 尊厳死3.尊厳死を迎えたいと思ったら・・・|あなたの尊厳が守られるためにすべきこと
- 尊厳死4.大切な人が尊厳死を望んだら|家族にできること
- 尊厳死5.大切な人を看取る|最期のときがきたら
もくじ
この記事を読まれる前に
持病の悪化などで余命が宣告されている場合、医師は「尊厳死を望みますか?」という質問をはしません。
現在の病状を説明し、苦痛の緩和の方法や最後に過ごす場所、延命治療などについて具体的に質問するはずです。
自分の最期を決定する時間が限られている人はその方法を別の記事で紹介しているので、そちらをお読みください。
「尊厳死を希望します」だけでは足りない
現在の日本で亡くなる時には、自宅でもそれ以外の場所でも多くの場合において医療や介護などの第三者の関わりがあります。
看取りのプロである医師や看護師はあなたの尊厳を守る努力をしてくれます。モノのように扱われるという心配はありません。
これを前提とすると「いい感じであの世に運んでくれる船に乗りたいです」と望めそうです。しかし残念ながらそのような素敵な船はありません。
尊厳死という言葉には定義がないからです。
「おいしいラーメンが食べたいな」ということに近いかもしれません。あなたの指すラーメンは、醤油なのか豚骨なのか。麺の太さやトッピング、ラーメンの温度や量まで考えると、その言葉だけであなたの満足するラーメンを提供できる人はいるでしょうか。
尊厳死を希望するだけではあなたが何を望んでいるのか伝わりません。なぜこのような分かりにくさを生んでいるのかは、別の記事で解説しているので参考にしてみてください。
「苦しいのは嫌だ」だけでも足りない
多くの人にとって苦しみは避けたいものでしょう。しかしその苦しみはどのようなものなのか、明確にしないと相手は理解できません。
極端な例を挙げるとしましょう。
「体が辛くても、心が辛くない方がよい。思い残したことがないようにしたい」という人がいます。逆に、「後悔や自責の念は耐えられるが、体が辛いのは我慢できない」という人もいるとします。
「苦しいのは嫌だ」とだけ言っても、何の苦しさを示しているのか自分以外には分かりません。またその発言をした本人ですら苦痛の正体を明確に理解していない可能性があります。
著者の親も「苦しくないようにだけしてほしい。あとはよきにはからって。」と言いました。まるで私を信用しているような発言ですが、任される側とすればさっぱり分からないのです。
自分らしい死を考えてみる
価値観は人それぞれです。どのような状況で死を迎えるのかによっても希望は異なるでしょう。家族の納得のためなら自分の希望は犠牲にしてもよいと考える場合もあるかもしれません。
あらゆる状況を想定しようとするときりがありません。
そこで、まずはゴールを想定してみましょう。自分が息を引き取る瞬間はどうありたいか、何を感じ何を思っていたいか。誰がそばにいてほしいのか。最後に誰かに何かを伝えられるとしたら、どうするか。目を閉じてイメージしてみましょう。
次にそのゴールに向かうには何を大切にすればよいのかを考えます。そうやってゴールから逆再生するように想像してみましょう。これを自分のなかでどれだけ深められるかがあなたが望む「尊厳死」への近道になります。
著名人のコラムなどを読んでみる
2017年に橋田寿賀子さんは、書著『安楽死で死なせて下さい』を発表しました。
2018年に亡くなられた樹木希林さんの言葉を集めた『樹木希林 120の遺言』という本もあります。著名人が死について書いた本やコラムを読んでみるのもひとつです。
本の内容をまとめた記事や本の批評はあまり意味がありません。ライターが伝えたいことに絞った内容では偏りがあるからです。
ネットの記事は広告料などを意識しすぎて本質からずれてしまうものもあります。全部読まなくても構いません。本でもコラムでも全文が載っているものを手にすることが大切です。
自分らしい死に協力してくれる味方を増やす

あなたの望む死を迎えるには協力してくれる人が必要になります。
家族はもちんですが、医師や看護師などの医療従事者だけでなく、福祉や経済的な支援も考えられます。あなたのことを理解し、それを支持してくれる人を増やしましょう。
「私の死に協力して」というのではありません。あなた自身を少しずつ知ってもらうのです。どのような人生を過ごし、何を大切にしているのか。何が恐怖の対象なのか。どのようなことに幸せを感じるのか。その方法のひとつに人生会議があります。
これについては後で説明していますが、その前に日々できることを伝えます。「いいな」「うれしいな」「素敵だな」と思ったことを口にすることです。
「散歩って気持ちいい」「これすごくおいしい」「ぽかぽかの布団、しあわせだな」「あなたのそういうところ好き」など、あなたがプラスに感じていることを言葉にすると、周囲の人はあなたが何を大切にしているのか少しずつつかむことができます。
そしてその積み重ねによってあなたを理解していくのです。
ここでポイントなのは悪いことではなく、「よいこと」に注目すること。悪いことを挙げるとあなたに関して負の情報が増えてしまします。〇〇を避けるというより、〇〇を引き寄せる、目指すという考えの方が死に対しても前向きに取り組むことができるからです。
人生会議という方法
人生の最終段階の医療・ケアを決定する方法として、厚生労働省は人生会議を推奨しています。アドバンス・ケア・プランニングというもので、話し合いを重要視したものです。
これも別の記事で解説しているので参考にしてください。
「ありがとう」「愛している」をもったいぶらない
「今までありがとう。幸せだったよ。」と言って息を引き取る。
テレビドラマのような死は残念ながらほとんどありません。ほとんどの場合、最期は意識がなくなり、話すことができなくなります。それがいつなのか誰にも分かりません。
感謝や愛情を表す言葉は話せるうちにどんどん口にしてください。
著者の祖父は病床で「〇〇(祖母の名前)、愛しているよ」と誰がいても臆することなく口にしました。海軍兵だった祖父。子どもにはとても厳しかったそうです。
その人が最期に口にした言葉が妻への愛。祖父が亡くなってからも祖母は「おじいさんはね、私のことを本当に大切にしてくれたのよ。」と誇らしげに語っていました。うれしそうに祖父を語る祖母が私は大好きでした。これはすべての人にあてはまることなのかもしれません。
自分らしい死は自分を開くことから
死はあなたひとりで完結できるものではありません。そばにいる人の理解や協力がなければ難しいでしょう。
尊厳死をしたいと思ったあなたの気持ちや理由を表現してください。大切な人と話すことが何よりも大切なのです。




















