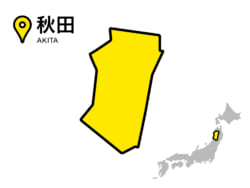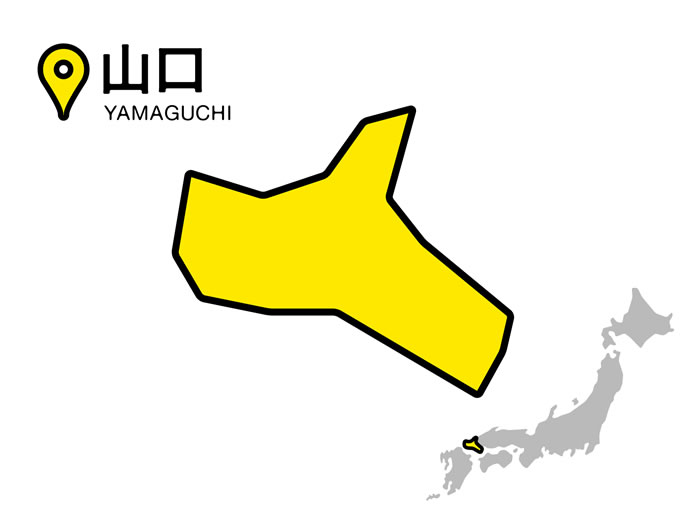
山口県は浄土真宗の門徒数が多いことから、俗信を取り込んだ葬儀を見ることはほとんどありません。
しかし、海の神を祀るなど神道の信仰を持つ角島だけは例外であり、友引の葬儀は避けるなどの俗信があります。
山口県でも家族葬が主流となりつつありますが自宅や寺院での葬儀も多く、地域の中の講中や隣組の手伝いが入ることも。
そのため講や地縁関係が強い地域では、現在も出棺の際にさらしの頭巾を被ったり、鐃鈸(にょうはち)を打ち鳴らしながら葬列の徒党を組んだりなど、「野辺送り」を見ることができます。
現在も葬儀の慣習が多く残る、山口県の葬儀をご紹介します。
もくじ
山口県の葬儀の特徴を紹介
山口県では葬祭業者のホール葬が主流となりつつありますが、それでもまだ自宅で葬儀を営む家も多いです。
北陸三県、広島県と並んで「真宗王国」と呼ばれるほど、浄土真宗の門徒が多い県であるため土葬時代から火葬が主流でありました。
浄土真宗の寺院がある地域では念仏講などの講中の活動が盛んであり、御詠歌の詠唱などで葬儀に携わることもあります。
浄土系に次いで禅系の寺院が多く、地域によっては現在でも鐃鈸(にょうはち)を打ち鳴らしながら練り歩く野辺送りの葬列がおこなわれています。自宅葬が多いこともあり、出棺前の茶碗割りなどの葬送習俗も残っています。
山口県は通夜振る舞い・お斎(仕上げ料理)ともに基本的に親族、葬儀を手伝う講中や近所の人たちのみしか参加しません。
下関市や宇部市など西部地方では一般会葬者への通夜振る舞いがおこなわれることもあり、遺族から案内があった時には一口だけでもいただくのがマナーです。
また、葬儀開始前に近親者のみで故人と最後の食事である出立ち膳(お斎)をいただく慣習があります。
下松市など県中部では、火葬中に精進落としを済ませる傾向にあります。
昨今、都市部では当日香典返しもおこなわれていますが、山口県では四十九日、もしくは年をまたぐ、または三ヶ月に渡る三月またぎとなる場合は三十五日の忌明け後に返礼品を送るのが一般的です。
全国的には1/3~半額返しが主流ですが、山口県では従来通りの半額返しが多い傾向にあります。
前火葬(骨葬)をおこなう地域がある|萩市
山口県の葬送儀礼は一般的な後火葬ですが、萩市の一部地域では前火葬による骨葬がおこなわれています。萩市周辺では近年まで土葬がおこなわれていた名残りです。
また萩市の曹洞宗と臨済宗の葬儀では、死後三日目におこなう開蓮忌供養を葬儀当日に行います。他地域ではこの法事は省略されて、初七日法要を繰上げておこなうのが主流となっていますが、萩市では現在も本来の儀礼通り開蓮忌供養が執り行われることが多いです。
その後の食事を一般的には精進上げまたはお斎と言いますが、萩市では「初度の膳」と呼んでいます。
焼香銭の慣習が残る
焼香銭とはお線香が高級品だった頃の慣習であり、線香を持参せずに葬儀に参列した際にお寺または喪家にお線香の借り賃として出していたものが形だけ残ったものです。
焼香銭の慣習は各地に残っていますが、中でも浄土真宗が多い地域によく見られます。
焼香台に賽銭箱、もしくはザルが用意されており、山口県の場合はそこに100円または500円硬貨を入れます。
また、山口県内には、小銭を白無地の小さいポチ袋などに入れて焼香台に置く地域もあります。
角島の葬送習俗と浄土真宗

角島には3つの浄土真宗本願寺派の寺院と、5つの神社があります。他宗派の寺院がないことから、浄土真宗の門徒の島といっても過言ではありません。
浄土真宗は死後即往生のため、基本的に魔除けの刃物や茶碗割りの慣習はありませんが、角島の浄土真宗の門徒の間には友引の葬儀を避けるなどの俗信が存在します。
仏教が入る以前より海の神を祀る神道の信仰がベースにあり、穢れの観念を持つ角島の地域性がその理由です。
通夜を夜伽と呼び、親族が持ち寄ったお酒、お菓子やおつまみを食べながら故人を偲びます。
精進上げはお斎、テゴと呼ばれる近隣住民の女性たちと親族の女性たちによって料理が用意され、葬儀後に親族とテゴの人たちとともにいただきます。
他地域では繰上げ法要として、葬儀当日に初七日法要が執り行われますが、角島では葬儀翌日におこなう慣習があり、現在でもその儀礼を守っている家も多いです。
角島にある俗信〜友引の日には藁人形を納棺
友引に葬儀をおこなう場合は、棺に身代わりとして藁人形を入れます。他地域でいうところの「友引人形」です。
また、四十九日までは死者の魂が近くにいるため屋根の上に上がってはいけない、餅をついてはいけないといった俗信もあります。
葬列の際は決して振り返らないとの決まりごとがあり、棺を担ぐ講中の男性4人の肩にはさらし布がつけられます。
俗信の一つに、妊婦が湯灌に携わるとお腹の子に障るといわれており、現在でも妊娠中の女性を立ち合わせることはありません。
寺院を中心とした講中が葬儀社代わりをしていた
角島にある仏教寺院は浄土真宗の3山のみで、島民のほとんどが門徒であり、地域ごとに組織されている講中に参加しています。一つの講中につき、約20軒ほどの家が参加していました。
2000年に角島大橋が開業するまでは、葬儀に必要な葬具、棺桶作りは講中の男衆、そして女衆は死装束とお斎の用意をおこなっていました。
葬祭業者による葬儀が主流となった現在でも、自宅または寺院で葬儀を執り行う場合は、昔ほどではありませんが講中と近隣住民によるお手伝い、講中によるお念仏と御詠歌の詠唱を葬儀で見ることがあります。
また、葬儀後の寺院へのお礼参りは手次寺だけではなく、他2寺院も廻ります。角島にある3つの寺院は島民たちにとっては門徒寺であり、いずれの寺院とも良い関係を保っているのです。
近年までは遺体の埋葬地である埋め墓とお参り用の参り墓を持つ両墓制でしたが、現在では一つにまとめられて単墓制となっています。
まとめ〜山口県に葬儀の慣習が今も多く残っているのは寺院と地域の結びつきが強く自宅葬が多いから
山口県は、どの宗派も檀家(浄土真宗は門徒)との結びつきが比較的強い県です。
現在でも各宗派の講を通して地域活動が活発に行われており、他地域と比べると文化風習が受け継がれやすい環境であると言えるでしょう。
その理由として、山口県は全国でも比較的高い持ち家率であることが挙げられます。
そのため葬儀も自宅、または地域内の集会所などを利用することが多く、昔ながらの地域コミュニティが保たれていることで葬儀の慣習も継承されているのです。